BATON
つなぐ、つながる
みんなの声
「学びたい」
その気持ちがあれば十分です。



Profile
2021年度 図書館司書コース・
学校図書館司書教諭コース 入学
広島県在住 /職業:会社員(マスコミ関係)
近藤 那美
大学在学中から憧れた司書への淡い夢を抱くも、
大学卒業後、広告代理店で営業職を5年勤める。
その後、転職するタイミングで、「やるなら今しかない」と心機一転、
資格を取得するために勉強することを決意する。
-
Q
通信教育部を選んだきっかけを
教えてください。「あの時資格を取っておけばよかった」
なんて言いたくない大学在学中から司書の仕事に興味があったものの、司書課程がなく当時は資格を取ることを諦めました。
しかし、社会人になり5年が経っても「大学生の頃、他大学に通いながらでも取っておけばよかった」という思いは消えませんでした。
「今そう思うならきっと10年後も思っているはず」と考え、今からでも資格の勉強をはじめようと決意しました。会社に勤めながらの勉強になるので、通信教育を選択。
知人やネットから情報を得て、いろんな大学の資料を請求し調べた結果、実績のある近畿大学に入学することを決めました。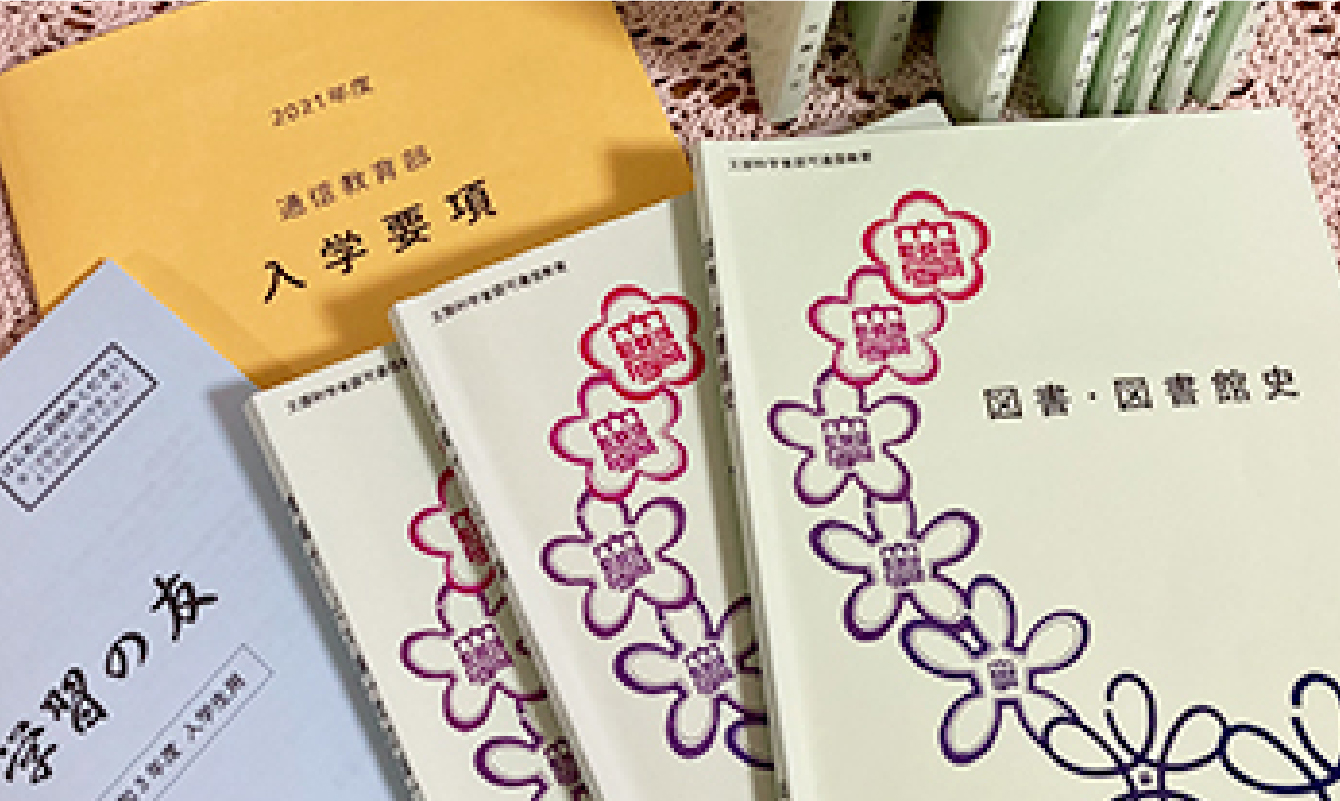
-
Q
学習についてなにか工夫をしていることは
ありますか?テキストの理解だけでなく、
図書館に足を運んでみて先生の講義を受けながら学習する「面接授業」と、テキストを自分で読み進めながら学習する「通信授業」があります。
面接授業では、オンラインで視聴できる「メディア授業」と、直接講義を受ける「スクーリング」のどちらかを選択することができ、私は日程や時間に縛られないメディア授業を選択しました。
通信授業では、基本的にテキストを熟読し、内容をきちんと理解することから始まります。その上で、実際に図書館に足を運び、どんなサービスが展開されているのか、どんな種類の図書があるのかなど今までと違った視点で見ることで、図書館や司書の仕事についての新たな発見もありました。
-
Q
困ったこと、壁に当たったと感じたこと、
その克服方法について教えてください。司書資格って、「本」の勉強だけじゃない!?
勉強を始めるまでは「司書は本に詳しい人」という漠然としたイメージをもっていました。
しかし勉強を始めると、利用者の要望を正確に汲み取るヒアリング力や、膨大な情報源の中から適切な情報を見つけ出す情報探索能力、あらゆる図書の内容を正しく理解し主題別に分類する力など、司書になるためには多くの能力が必要なのだと知りました。
中には苦手に感じる科目もあり、「自分は司書には向いていないかも」と思うこともありましたが、掲示板やSNSで同じように悩みを抱える人が多くいることを知り、励まし励まされ乗り越えました。
また図書館でさまざまな本を借り、勉強でわからないことは随時先生に質問し、理解を深めることで解決しました。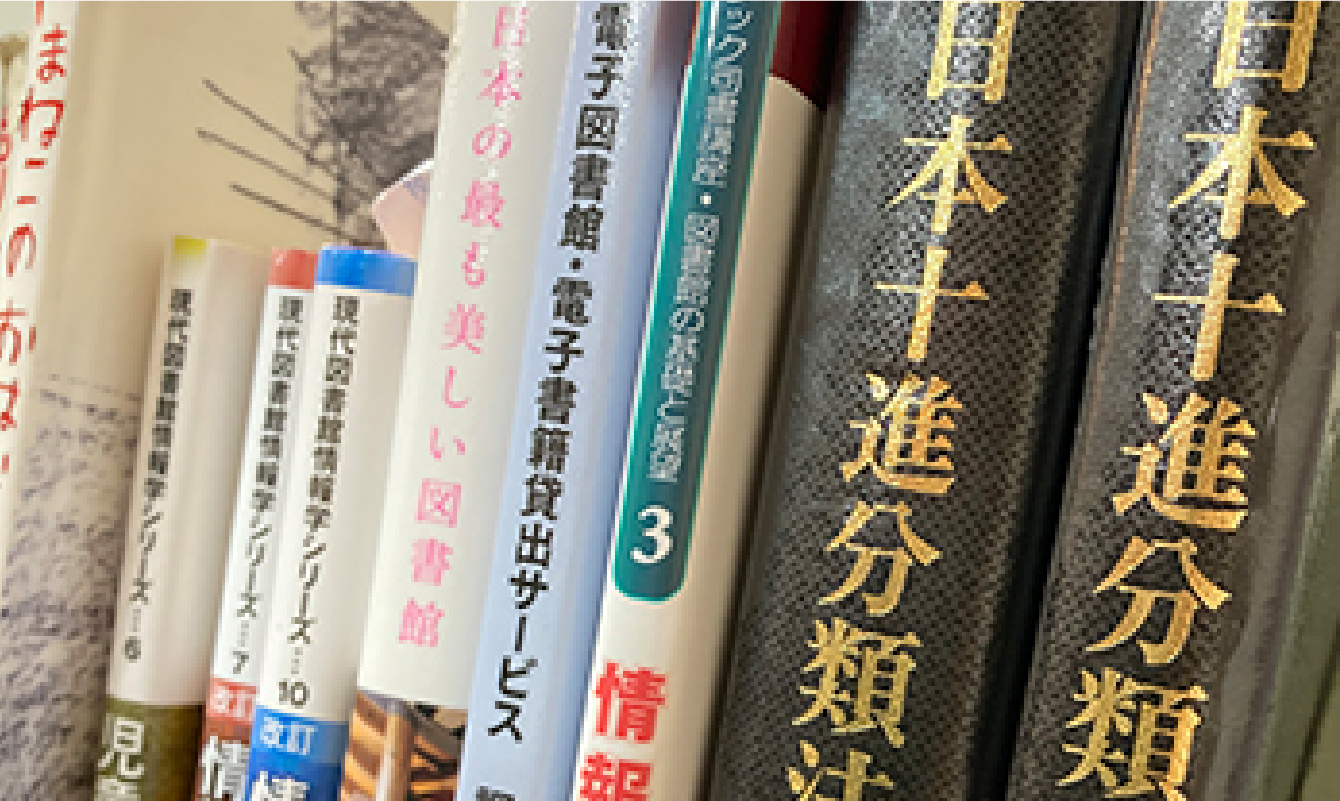
-
Q
学習方法について
教えてください私は13科目履修し、最初はどの科目から手をつけてよいか迷いましたが、入学説明会でおすすめの学習順序を教えていただき、それに沿って学習しました。そうすることで、段階を踏んで着実に知識を身につけることができました。
日中は仕事をしているので、勉強する時間は基本的に夜か休日です。早い人では半年程で修得される人もいますが、私は働きながらということもあり、1年という期限を設定した上で、「いつ、何の科目の試験を受けるか、そのためにはいつまでにレポートを仕上げておく必要があるのか」とスケジュールを逆算して勉強に取り組みました。そうすることで、焦らずに学習を進めることができました。
また、テキストを読み込む前に、各科目のレポートの設題を確認することで、どこに気を付けて読み進めればよいかがわかり、要点を抑えながら効率的に学習することができますよ。
今回のバトン

レポートの再提出が続いたとき、
どのように打破できましたか?


レポートの合否に関わらず、先生から講評をいただけるので、まずはそれをもとにレポートを修正していきます。
その上で「きちんと設題に対しての問いになっているか」「情報として何が足りていないのか」「固定概念に囚われていないか」など、多角的な視点から考え、テキスト以外の参考書にも目を通すことで情報を取り入れました。
また、テキストを読み込み理解することは大事ですが、実際に図書館に足を運んだり、自分の目で確かめることはもっと重要です。
レポートに行き詰まったら、気分転換も兼ねて近くの図書館へ足を運んでみてください。図書館サービスに関する新しい発見があるかもしれません。
次回のバトン

気分転換はどのように
されていましたか?
一覧に戻る












